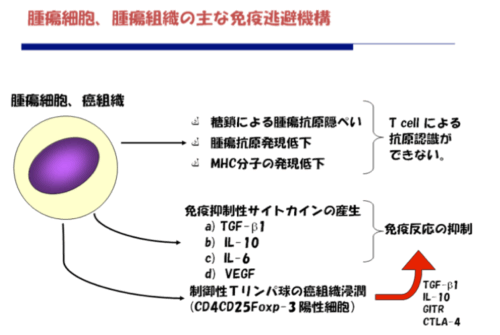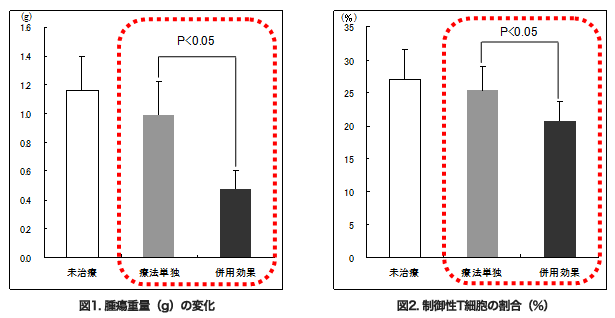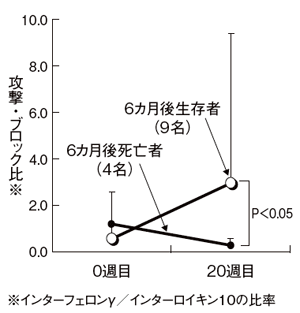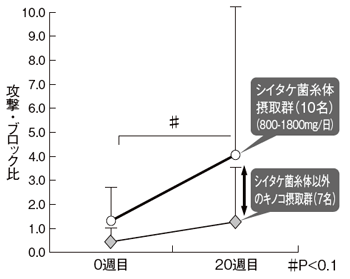4/15 制御性T細胞に着目した免疫細胞療法
免疫細胞療法というのが、試みられてすでにかなり経っているが、なかなか民間療法の域と出ない。理由はどこにあるのだろうか?
個人的に、中立的な立場から見れば、抗がん剤も免疫細胞療法も共に個人差の大きい治療法なので、どっちもどっちだろうか?保険が効くか効かないかくらいの差しか感じないのは、化学療法が効かなかったヒガミかな?
免疫細胞療法は、よく試験管の中では理論通りに作用するのに、実際に人体に試すと想定したほど効果が出ないという。この差はどこから来るのであろうか?
よく言われるのは、癌細胞による免疫細胞の制御ではないだろうか?
(出所:京都府立医科大学HP)
癌細胞により、
- 腫瘍を特異的に攻撃するT細胞(CTL)から身を隠す。
- 制御性T細胞(Treg)の数を増やし、免疫機能を抑える。
(Dudley ME, et al, J Clin Oncol, 2008)
ような状況が見られ、試験管の中と異なり、理論通りの働きができないと考えられるという。
次に、小林製薬のHP上に、免疫細胞療法を実施する際に、この制御性T細胞の血中数を減らすように試みたところ、がんペプチドワクチン療法の効果が高まったとの報告がある。
なんとなく、それっぽく聞こえるが、癌の治療法でこの制御性T細胞が注目されることは少ない。
この制御性T細胞ががん患者では、有意に健康体の人より多いという。これを健康体の人並に戻せば、免疫細胞療法等も理論的に効くのでは?という考えが小林製薬のHPの内容だ。大阪大学でも制御性T細胞を抑制することで、抗腫瘍免疫力を上げることが可能とある為、理論的にはありえそうである。
では、制御性T細胞をどうやって減らすかというと、なかなか有意義な資料は見つからない。小林製薬のHP上では、α-グルカン等を含む「シイタケ菌糸体」で、制御性T細胞の割合を減らしたとある。
ここの理論的背景がなかなかわかりずらい。経験則的に、シイタケ菌糸体が免疫力を上げるというのは、アガリスク等が民間療法で用いられていることからも類推できるが、こと制御性T細胞のことに関しては、ほとんど調査もない。
この制御性T細胞の抑制となると、医学的にあまり臨床研究は進んでおらず、どうしても民間療法に行ってします。しかも、たいていがキノコの類である。
がん情報サポートセンターというHPで、福岡大学の永山教授も、同様に再発予防における制御性T細胞の役割に注目しており、やはりシイタケ菌糸体がこれの抑制に効果があるという。
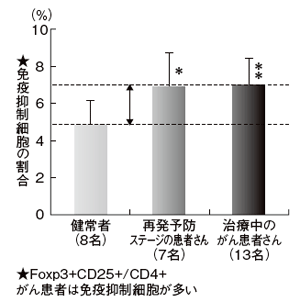
左の図は、HPからの抜粋だが、健常人に対して、治療中の患者はもとより、寛解後の再発予防ステージの患者においても免疫抑制状態にるという。資料の提供元から考えて、若干バイアスが入っている可能性があるが、少なくとも腫瘍の塊が体内から取り出されただけでは、当面は免疫抑制状態から解放されない可能性がある。
次の図は、免疫細胞を活性化するインターフェロンγと、免疫抑制細胞が出すインターロイキン10という生理活性物質の比率に注目したものだそうだ。インターフェロンγ/インターロイキン10の比率は免疫の「攻撃・ブロック比」ともいうべきもので、値が大きいほど免疫がうまく働き、逆に、値が小さい場合は免疫が無力化された状態と解釈するそうである。で、生存した人と死亡した人と免疫力は有意に差が出ているとしている。
で、シイタケで免疫力が上がったという予想通りの図。
|
Sponsored Link |
Sponsored Link
”がんの治療を終え、再発予防ステージにいる患者さんにとって、大きな厄介者は免疫抑制細胞で、シイタケ菌糸体の免疫抑制細胞を減らす作用の今後のさらなる研究が期待される。”と締めくくられている。