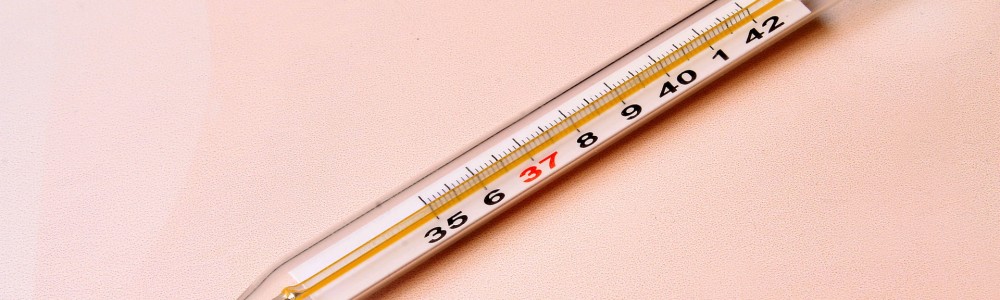発熱のメカニズムについて調べてみた
NK細胞の点滴(ここの療法はANK細胞療法と呼ぶそう)を実施するに伴い、危惧されている発熱について調べていた。
よく、”40度を超えるような高熱がでたら、脳障害になる可能性があるから、要注意だ。その為、発熱したら解熱剤を早めに処方すべき”という話をよく聞く。実際のところ、この辺りはどうなのか?
多くの小児科のサイトを見てみると、解熱剤については、あまり万能薬的な扱いではなく、一時しのぎだと言い切っている。しかも、解熱剤の種類によっては、解熱剤による副作用で後遺症が残るといったこともあるという。
しかし、実際の診察現場では、解熱剤の処方が多いという。なぜか?これは親から解熱剤を出してほしいという強い要望があるから、出しているというのが本音だそう。小児の開業医にとって、発熱は、診察の大部分を占めるそうだ。
医師としては解熱剤が必要ない場合でも、解熱剤等を出さないと、親が納得せず、次回からその診療所に来なくなるそうだ。これでは、開業医として生計が成り立たない為、親のニーズをくむ形で、解熱剤を多用するようになったそうだ。
高熱の発熱で、頭がおかしくなる(脳障害が残る)ことがあるか?といえば、答えはないそうだ(あくまであっちゃんパパが調べた結果ですが、、)。以下は、あるHPの引用だが、
幼児では、39度以上の発熱は、めずらしいことではありません。しかし、脳内には体温上昇を抑制する物質(解熱性ペプタイド)が安全弁として働くため、通常の発熱では、体温は、41.5℃を越えることがないようになっており、脳障害はおきません。脳障害が起こるのは、髄膜炎・脳炎など脳自体に発熱の原因がある場合です。
出所:NPO法人 東京中央ネット
そもそも、発熱の原因は何で、なぜ起こるのか?これも同じHPからの引用では、
発熱の原因:多くの場合、感染による発熱です。感染以外にも、熱射病・日射病、脱水症、白血病等の悪性腫瘍、川崎病等から、恐怖や不安といった心の反応からの発熱にいたるまで、いろいろな原因があります。
発熱のメカニズム:体温は、熱産生と熱放散のバランスで、調節されています。ウイルスや細菌などの病原体が体の中に侵入して来た時に、免疫系の細胞が働き、サイトカインという物質が産生されます。
サイトカインは、体内のプロスタグランジン産生を促がし、プロスタグランジンが、脳の視床下部というところにある体温調節中枢に作用します。
プロスタグランジンの量に応じて、セットポイントという体温設定が上昇します。そして、視床下部から、熱を産生する指令を筋肉に送る一方、熱の放散を抑制する指令を皮膚に送ります。
熱産生の筋肉運動は、悪寒のふるえ(戦慄)としてみられます。皮膚では、鳥肌が立ったり、発汗が抑えられ、血管が収縮し血液の量が減るため、手足が冷たく蒼白にみえます。
体温が上昇し、セットポイントまで達すると、この体温で体温調節が行われ、高体温が維持されます。高体温維持の段階では、余分な熱を放散するために皮膚血管が拡張し、発汗も起こります。この時手足はあたたかくなります。
付け加えると、体温上昇には、二つのメリットがあります。感染等で、体内に異物が侵入してくると、体内の免疫細胞を活性化して、撃退しようとしますが、免疫細胞は体温が上昇すると活性化するといいます。
また、細菌等は高温では、弱るとも言います。すなわち、発熱は体の防衛反応であり、それ自身が、体に害を与えることはないと考えられます。
すなわち、発熱それ自身は、脳が体の防御反応として、意図的に体温を上昇させているものであり(通常は40-41度まででコントロールされるようだ)、その体温上昇により、脳が破壊されることはない(冷静に考えれば、自分で焼身自殺するようなものだから)。
では、どういった場合に、脳障害が残るのか?これは、熱ではなく、発熱の原因である、脳炎、髄膜炎等によるものだという。
こういった場合、同時に40度を超える発熱やけいれんを伴う為、高熱がでたら、脳炎、髄膜炎等の可能性も視野にいれ、早め早めの対応で、後遺症の可能性を未然に防ぐというのが、原因と結果であるが、なぜが高熱→後遺症といった連想が強烈にあるように思われる。
次に、では発熱自身が特に体に悪いものでないのであれば、解熱剤はいったい必要なのか?ということになるが、答えはケースバイケースと言えるようだ。
基本的に、発熱があっても元気であれば、解熱剤は必要ないそうだ。ただ、ぐったりしていた場合等に、それが原因で食欲不振、飲水ができなく、更に状況の悪化が懸念される場合には、解熱剤による体温の低下で、活力が戻り、栄養補給が可能であれば、推奨されるよう。
目安は、38.5度以上であれば、使用を検討するそうだ。しかし、これも一時的でまた体温は上昇することが多い為、その際に体力を消耗することを考慮すべきという。
|
Sponsored Link |
Sponsored Link
結局は、体の免疫力(自然治癒力)で回復するというのが基本であり、これを補佐するように対処することが重要という。